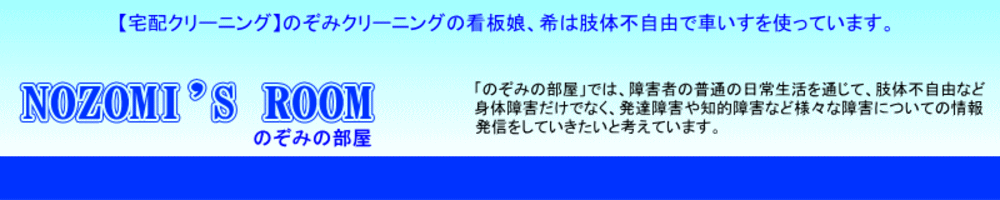
 オススメ映像セレクション |
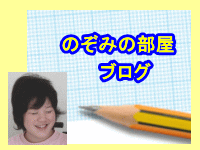 のぞみの部屋ブログ |
 バリアフリーの部屋 |
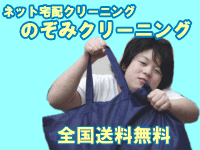 のぞみクリーニング |
 外部リンク集 |
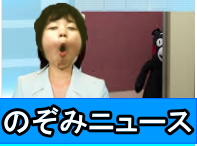 のぞみニュース |
 メールはこちらへ |
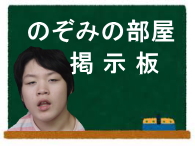 のぞみの部屋掲示板 |
肢体不自由の原因、症状、そして少しでも改善させるために何が出来るのか。
同じような障害を持つ方もいられると思い、調べたものを列記します。
痙直についての記述は、 都立城北養護学校の自立活動部、理学療法士の
豊田利郎先生の学習会の記録から引用させていただきました。
受精から生後4週までに何らかの原因で受けた脳の損傷によって引き起こされる運動機能の障害を指す症候群。原因として、周産期仮死、
低体重出生等が挙げられる。
脳の損傷部位によって、以下の4タイプに分類される。
・アテトーゼ型・・・大脳基底核が損傷されたケースで不随意運動を特徴とする。
・失調型・・・・・・・・小脳もしくはその伝導路が損傷されたケースで四肢麻痺、運動不安定性などを特徴とする。
・痙直型・・・・・・・上位運動ニューロンが損傷されたケースで、四肢の筋緊張の亢進を特徴とし、折りたたみナイフ現象が見られる。
障害が現れる部位によって片麻痺、対麻痺、四肢麻痺、両麻痺などに分類される。
視覚、認知障害、斜視を合併することが多い。
・固縮型・・・・・・・・錐体外路の障害があり、四肢麻痺が出現する。関節の動きは歯車様となる。
大脳皮質運動野や脳幹に始まり、運動情報を下位運動ニューロンに伝える経路、またはその神経細胞。
目標器官を直接刺激する下位運動ニューロンに対する概念である。
上位運動ニューロンは大脳からさまざまなレベルの脊髄に向かい、そこで神経信号が下位運動ニューロンを通して筋に伝えられる。上位と
下位の運動ニューロンの間の信号伝達は、シナプスにおいての神経伝達物質のひとつであるグルタミン酸が上位運動ニューロンから放出
され、それが下位運動ニューロンのグルタミン酸受容体によって感知される。
四肢の関節を他動的に動かそうとすると強い抵抗がみられるが、その後抵抗が急速に弱くなるという現象のことである。
折りたたみナイフに力を加えると急激に閉じる様子に似ているため、この名がついた。
上位運動ニューロン障害に特徴的な反応のひとつである。
片方の目は視線が正しく目標とする方向に向いているが、もう片方の目が内側や外側、あるいは上や下に向いている状態のことをいう。
普段は正常だが、時々斜視の状態になるものもある。
筋緊張の評価で、動きにくくて抵抗があるときは痙性、痙直という。
痙性、痙直が体のどの部分に広がっているかで、大きく分けて四肢麻痺(全身)、両麻痺(下半身)、片麻痺(半身)の違いがある。
同じ痙直型四肢麻痺でも、障害が軽くなっていくと、上肢が使えるようになり、痙直型両麻痺の状態になっていく。逆に痙直型両麻痺の障害
が重くなっていくと上肢も使いづらくなり、痙直型四肢麻痺の状態になっていく。両麻痺と四肢麻痺の境目はわかりにくい。
筋緊張の状態も様々で、体の部分で全ての緊張が強いとは限らない。逆に、ある部分の緊張が低いこともある。
例えば、四肢の緊張が高く、体幹の緊張が低いという場合もある。
また、同じ肘関節でもそのときによって曲がる緊張が強くなっているときと、伸ばす緊張が強くなっているときがある場合もある。
基本的には低緊張だけれども、痙性を持っている場合もある。
痙性、痙直というのをよく見てみると、痙性が強い筋があり、その拮抗筋というのは、筋が働きにくいのが特徴である。痙性のある筋というの
は必ずしも強く働くというのではなく、痙性がある筋なのに力は弱いという場合が多い。
また、痙性のある筋は、力が入って短くなっているときは支持力があるが、伸ばされると力が入らないということもある。
例えば膝が伸びきっていると体重を支えられるのに、膝が曲がってくると支える力がない場合などがある。
それほど重度でない場合は、自分から動くことが課題になっていく。動くことによって痙性が高まったりする。例えば座位でバランスをとる時
に足が交差したり、膝が曲がってイスの内側に入ったりする。
連合反応といって、例えば、四肢の動きによって上肢の痙性が高まったりする。いつも同じような動きしか出来ないことが多い。
例えば、四つん這いの時は両足を引きずったりする。特定のある筋肉、ある関節を選択的に動かしにくい。
一般的に痙直型に対しては、動きを入れることを大切にして、同じ姿勢で固定することを避けるようにする。
その子の筋緊張や運動のパターンの特徴を見る。動いたり、いろんなことが出来るようになっていったりするが、運動発達や日常生活の向上
を促すときに、出来るだけトータルパターンの動きではない分離した動きを出すようにする。
トータルパターンというのは、全身的な動きが出てしまうような動きで、例えば座位でバランスをとろうとすると、全身が伸展とともに股関節
周辺の緊張が高まり、足が交差してきて、結果的にバランスを崩したりする動きのこと。
それに対して、分離した動きというのは、座位で体が伸展しながらも、股関節が外転したり、外旋したりする動きが出ること。
また、連合反応が出やすいのでそれを防ぐことを考える。そのためには過剰な努力にならないように注意する必要がある。
連合反応とは、ある部分の動きを努力して行うことによって、その部分だけでなく、別の部分も痙性が高まる動きが出てしまうことをいう。
例えば車いすを一生懸命こいでいると下肢が緊張してピーンと伸びてしまったりすること。また、例えば、手を使った腹這いで下肢を引き
ずっていくと、上肢、下肢ともに緊張が強まったりする。
臥位・・・バルーン上の腹臥位、ロールの上での背臥位での体重移動、側臥位での左右の体幹を引き伸ばす
座位・・・椅子に跨った座位、後ろや横にもたれた座位、床座位で上肢の支持
立位・・・バルーンから足をつけて立位になる、後ろにもたれた立位
生活の中で、床から起き上がるときは、側方に手をついて体重をかける。寝返りのとき、うつぶせになるときに肘立てになる。立つときには
足に体重がかかるようにする。
両麻痺になると、重度でなければ独歩まで至ることが多い。
骨盤から下が動きにくく、健常児の赤ちゃんのとき行う背臥位のキックでは、動いても十分な範囲を動かすことが出来ない。
腹部の筋緊張が低いことも特徴。
動くパターンも股関節が内転、内旋し、膝は屈曲し、足関節は底屈の動きになってしまうため、様々な動きが出来ない。
這い這いも下肢を引きずるか、片方の下肢だけでキックする。
立つようになると股関節の内転、内旋、膝の屈曲、足の底屈の状態で立つ。左右差が出てきて、片方の足に多く体重がかかる。
座位は、腹筋が弱く骨盤も固定できないで後傾または前傾位になる。このときに上肢を使おうとしても、骨盤後傾の場合は手が前に出ない。
骨盤前傾の場合は体が支えきれず前に倒れてしまう。上肢の動きは使えとしても、手指の伸展、親指の対立がしにくかったりする。
立位をとると、重力でつぶれたような姿勢になってしまう。
歩行すると、下肢と骨盤の分離がなく、骨盤、体幹と下肢を同時に振り出してしまう。
両麻痺は伸展タイプと屈曲タイプで分けることが出来る。
伸展タイプは、より機能が良いので歩くときに骨盤を前傾位で固定し、腰椎の過伸展を用いて体幹を進展させて、左右に体重移動しな
がら歩くことが出来る。ただし回旋を用いた歩行はできない。
屈曲タイプは、伸展タイプに比べて伸展の力が弱く、骨盤を前傾、腰椎を過伸展位にもっていくことができず、体幹が伸展できない。体重を
左右に移すことが難しく、後ろにしりもちを着くか、前に倒れてしまうことがある。独歩は出来ても不安定で、杖歩行にとどまる場合も多い。
子ども自身が自発的な運動をするようにしていくことが大切。屈筋痙性が強い場合は、動きが出にくいので、これを抑制する。そして、伸展、
外転の動きを出すようにする。特に股関節の伸展は大切。
回旋の動きが苦手なので、座位や立位や歩行で、骨盤と体幹、骨盤と下肢、上肢と下肢等の間に回旋の動きが入るようにする。
立位では、体重が前にかかってしまうので、伸展しながら後に体重を移すようにする。このとき骨盤は前傾から後傾にもっていくようにする。
その上で、前方、後方、側方の体重移動ができるようにする。
次に一側下肢での体重支持の練習をして、歩行の準備をしていく。抗重力の活動が十分できることが必要。
また、左右差が生じやすいので、これを出来る限りふせいでいく。
上肢は、引き込んで使うことが多いので、上肢の使い方を学習していく必要がある。座位で上肢を使うときに、体幹、骨盤が固定できるように
する。適切な上肢の動きによって、よい姿勢や動きを引き出すこともできる。
両麻痺は、日常生活で出来ることが多いが、立位も座位もバランスが不安定で、そのため上肢も使いにくかったり、連合反応が起こったり、
痙性が強まったりすることがある。日常生活の動作を指導する必要もある。
四肢麻痺のときと同じようにバルーンを用いた痙性の抑制。
腹臥位で、股関節、体幹の伸展。腹部、肩甲帯、上肢の支持性を高める。
背臥位でブリッジ。片足で指示したブリッジ。膝伸展位のブリッジ。
座位で骨盤の前傾。(膝を介助して、骨盤を前後からはさんで持ち上げるように、一度後傾させてから前傾へ)
立位で手で支えながら骨盤を前傾位から後傾位にもっていく。
立位で後方にもたれて体重を後ろに移す。左右の体重移動。
足を前後に開いて立ち、前側の足を介助者の膝の上にのせる。
上肢の使用。両手でボールを持ち上げて入れる。筒を机の上で転がす。鉛筆削り。
のぞみの部屋トップページに戻る